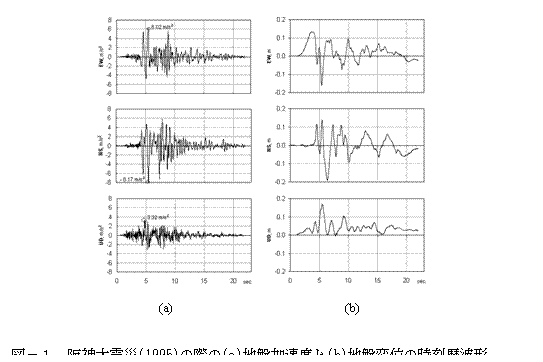|
最近の研究の紹介:木造住宅の崩壊解析による耐震診断−新しい精密・動的な耐震診断と補強方法− |
|||
 |
木造の建売/注文住宅の崩壊解析による耐震診断法を開発。住まいの新しく精密で動的な耐震診断法であり、設計図から建物の欠陥を発見。シミュレーションで3次元(d3)アニメ動画表示。建設業者/メーカーによる耐震リフォーム/耐震補強/地震対策の費用を安く抑え、地震に強い一戸建て木造の新築/中古/建売/注文住宅の建設/家づくり/リフォーム/耐震改修を達成。 |
.png) |
|
論文著者名:タイトル
|
埼玉大学開放デー(2008年5月24日)講演会資料 埼玉大学地圏科学研究センター 教授 川上 英二 |
||
|
4.入力地震動
本解析では、地震外力として阪神大震災の際に神戸海洋気象台で観測された図−1の波形を使用している。左が加速度波形、右が変位波形である。上から東西方向、南北方向、上下方向の記録である。最大加速度は約0.8G (G:重力加速度)、最大変位は約0.2mである。この加速度波形から求められる気象庁発表の(計測)震度は 6.4 (震度6強)であるが、この付近での建物の全壊率は約3%、半壊率は約55%であり、震度6強にしては被害が少ない[境ら(2002)]。 本解析では、上記の観測波形そのまま(1倍)の地震動に加えて、振幅を1.5倍したもの(最大加速度:約1.2G 、最大変位:約0.3m)、および、振幅を2倍にしたもの(最大加速度:約1.6G 、最大変位:約0.4m)を使用している。境ら(2002)の方法により木造建物に対する震度を求め直すと、観測波形の震度は約6.1(震度6弱と震度6強の間くらい)であり、また、振幅を1.5倍したものは約6.4(震度6強、木造建物全壊率:約25%)、振幅を2倍したものは約6.7(震度7、木造建物全壊率:約40%)である。 ただし、震度6弱とは震度5.5〜6.0、震度6強とは震度6.0〜6.5、震度7とは震度6.5以上のことを示している。震度6と7の違いは数字の6と7からイメージされるような1、2割の違いではなく、振幅が2、3倍違っていることに注意する必要がある。 将来、家がどの程度の地震に襲われるかは、確率的にしか判らない。しかし、その際、周囲の家の数%(1割弱)が倒壊した場合に、自分の家が倒壊しないためには、震度6弱(本解析で1倍)でチェックすれば良い。また、周囲の家の約3割が倒壊した場合に、自分の家が倒壊しないためには、震度6強(本解析で1.5倍)でチェックする必要がある。更には、周囲の家の5割(半分)程度が倒壊しても、自分の家が倒壊しないためには、震度7(本解析で2倍)でチェックする必要がある。
(続き) |
|||